野菜と果物の違いはどこで区別するのですか? たとえばすいか、メロンは野菜、果物のどちらですか?
農林水産省では次のように説明しています。
野菜と果物(果実)の分類については、はっきりした定義はありま
あるものを野菜に分類するか果物に分類するかは、国によっても違
生産分野においては、一般的に次の特性を持つ植物が野菜とされています。
■田畑に栽培されること(栽培されていない山菜などは野菜と区別することが多い)
■副食物であること
■加工を前提としないこと(こんにゃくのような加工を前提とするものは野菜としていない。漬物のように原料形質がはっきり残っているものや家庭における簡易加工は加工に含まない)
草本性であること。 しかし、どの定義も確固たるものではありません。
■農林水産省では、果実を、生産や出荷の統計をとる上で果樹として分類しています。この果樹は、木本性などの永年作物のことをいいます。
■副食物であること
■加工を前提としないこと(こんにゃくのような加工を前提とするものは野菜としていない。漬物のように原料形質がはっきり残っているものや家庭における簡易加工は加工に含まない)
草本性であること。 しかし、どの定義も確固たるものではありません。
■農林水産省では、果実を、生産や出荷の統計をとる上で果樹として分類しています。この果樹は、木本性などの永年作物のことをいいます。
なお、いちご、メロン、すいかなどは野菜に分類されますが、果実的な利用をすることから果実的野菜(果菜類)として扱っています。
またゆずやすだちは木本性で永年作物ですから本来なら果樹ですが、市場統計では用途が野菜ですから野菜に分類されています。


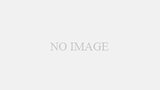
コメント